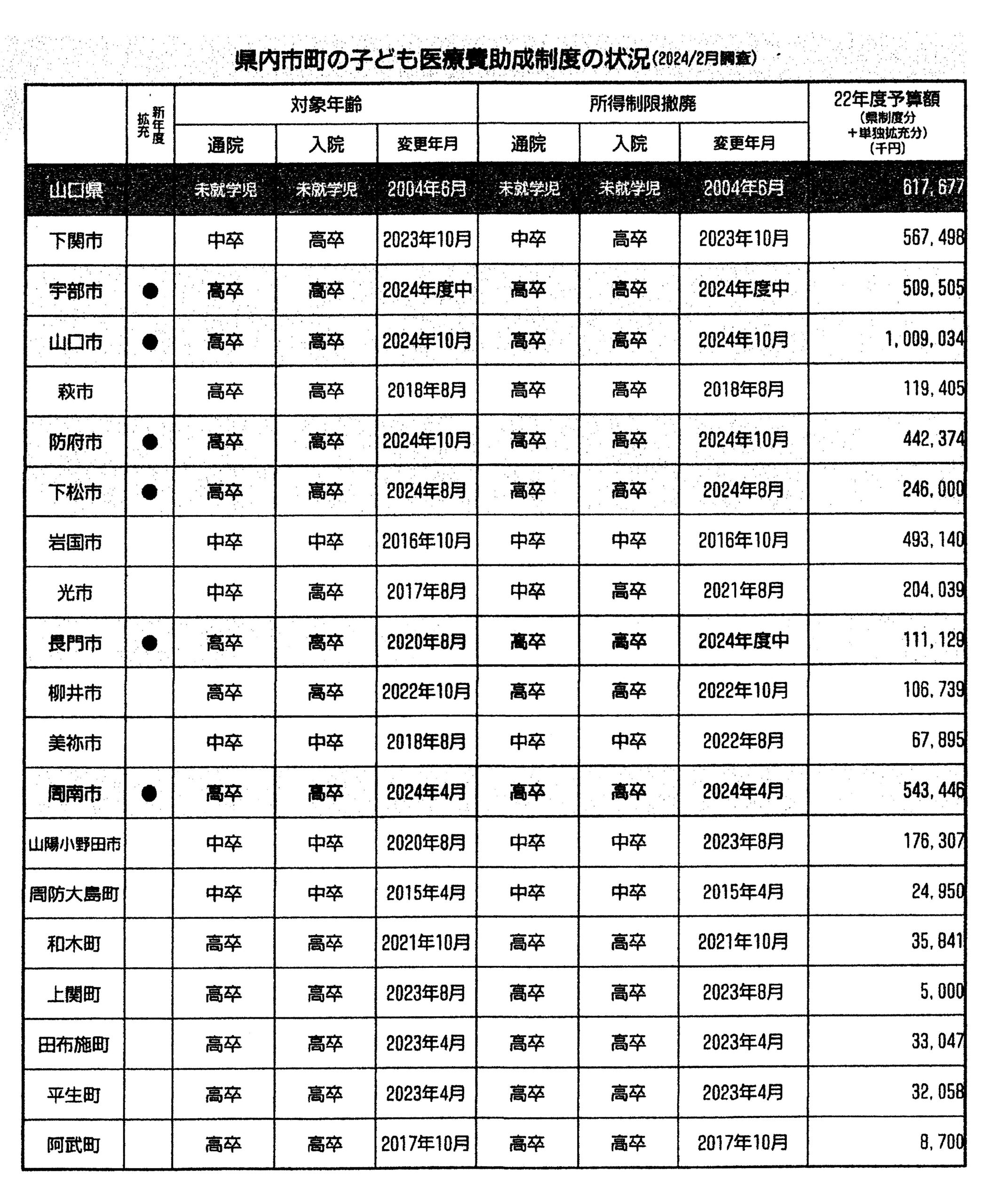脱原発について・・・(1)使用済み核燃料の中間貯蔵施設
能登半島地震で志賀原発は、外部電源の受電用系統が一部使えなくなるなど、一つ間違えば過酷事故につながる恐れがあった。また、震源地は珠洲原発建設計画予定地だった直近で、地震で地盤が数メートル隆起した。原発があったら、配管などが壊れて、ましてや取水口も隆起して冷却が全くできず大事故となり、逃げられない住民は福島原発事故以上に被爆した可能性は否定できない。と環境経済研究所の上岡直美代表は言っている。計画がとん挫していなければ大惨事になっていたであろう。
福島原発事故もまだ終わっていない。廃炉の展望は見えないし、故郷へ帰れる見通しも立たないままだ。再稼働は絶対に許されない。地震国日本では原発運転は非現実的で危険極まりないことを国民全体で再確認すべきである。
そこで脱原発について、お尋ねです。
11月定例県議会終了後の12月26日に、村岡知事は記者会見で、原発本体と別の原発の使用済み核燃料を保管する中間貯蔵施設が併存する場所は国内にないとして「過大な負担」との認識を示し、また、2001年4月23日に当時の二井知事が、上関原発の設置計画に関し、6分野21項目の意見書の中に、「使用済み燃料の貯蔵・管理について、発電所内での新たな貯蔵施設にたよらないで済むよう、また、発電所内での貯蔵管理が長期にわたらないよう、適切な対応を講じること」の意見の表明をしており、そして、村岡知事は、二井元知事のこの<意見を踏襲する考えも示されました。
また、2月13日開会の福井県議会において、関西電力が使用済み核燃料を3原発敷地内で乾式貯蔵することの是非についての議論が行われ、2月16日の代表質問で自民党会派は、「乾式貯蔵施設については、永遠に保管されるのではないかとの不安の声もあるが、保管期限を求める考えはあるか」と質問。また、越前若狭の会からも、「県として保管期限及び貯蔵容量を増加させないことを条例で定めるべき、明文化された担保が必要だ」と質問。
この代表質問に対し、杉本福井県知事は「県内保管の全ての使用済み核燃料は、保管方式にかかわらず再処理するために搬出される」の建前論でいなしています。
気になるのは、「乾式貯蔵施設で保管する使用済燃料については、関西電力は2030年頃に設置する中間貯蔵施設に、速やかに搬出をするというふうに言っている。まずは申請了承の判断をすることが必要ですが、最終的には、(原子力規制委員会への)事前了解を判断するまでには具体的な搬出時期の考え方を、関西電力に確認をしたい」との、杉本福井県知事の答弁です。
暗に、関電に県外での中間貯蔵施設を操業させる計画の実行を迫る形となっています。
名指しこそされていないが、この県外が上関であることは明白です。
関西電力は、これまで管内の自治体に働きかけてきたが名乗りを上げる自治体は皆無という状況の中で、山口県が何故、使用済核燃料を押し付けられなければならないのか。一刻も早く、上関町への使用済核燃料の中間貯蔵施設建設拒否を、村岡知事は表明すべきです。所見を伺います。
産業労働部理事答弁・・・脱原発についてのご質問のうち、使用済核燃料の中間貯蔵施設についてのお尋ねにお答えします。
上関町における使用済燃料中間貯蔵施設については、現在はあくまでも、施設が立地可能なのかどうか、その調査が実施されているところであり、現時点、当該調査の結果や施設に関する具体的な計画もなく、県としての見解や対応を申し上げる状況にはないものと考えています。