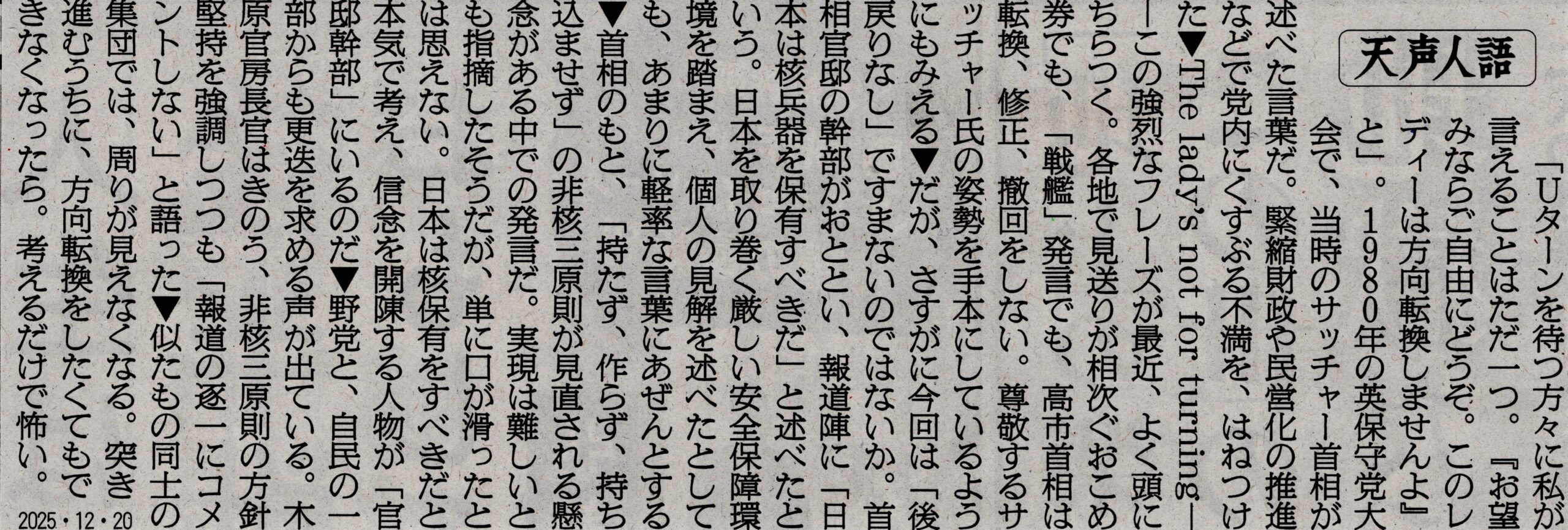カテゴリーアーカイブ: 議会報告
原発に係る電源立地地域対策交付金について
25年11月県議会
6、原発に係る電源立地地域対策交付金について
上関町長の新たな地域振興策の要請を契機に浮上した使用済み核燃料中間貯蔵施設だが、実は、原発そのものが地域経済波及効果に劣る点については電源三法・電源立地交付金制度について審議された1974年5月17日の衆議院大蔵委員会で原発建設が着工できない事由を問われ、当時の資源エネルギー庁長官は、「第一に、環境保全の問題、原子力の安全の問題に対します地元住民の不安感が根強い。第二に、発電所が典型的な装置産業でして、ほかの産業と比べて雇用機会の増加等による地元の振興に対するメリットが非常に少ない.また、発電されました電気の大部分は地元には落ちませんで、遠隔の大都市等で消費されると言うことに対する地元の不満感といったものが大きな原因である。」と、答弁しています。
原発立地と地域経済・自治体財政に関する多くの論考があるが、共通しているのは、原発立地地域では建設業、宿泊業、飲食店、サービス業の就業者数が一時的に増えるが、農林水産業や製造業は減るという共通した特徴がある。例えば新潟県柏崎商工会議所の調査結果を精査すると原発関連の仕事に強く依存している企業の比率は4割には遠く及ばずせいぜい1割程度であると報告されている。
さらに、原発が立地すると人口が増えるという議論も、ことごとく否定されている。現に、上関町の人口減少も顕著である。
しかも、原発立地地域の代表格であった福島県の双葉町がフクシマ原発災害前に財政破綻を起こしていた。交付金による公共施設整備を重点的に行った結果、後に発生するランニングコスト(人件費、水道光熱費など)の負担増大で財政危機に陥っていたことに留意すべきである。
県と上関町に交付されている上関原発に係る電源立地地域対策交付金の原資は、電気料金に含まれており、この分の支払いは拒否することはできず、電源開発促進税として電力会社が徴収し、 1,000kwhにつき375円を国の一般会計に納入。国は、これを特別会計の電源開発促進勘定に繰り入れて電源立地地域へ交付金を交付する制度になっている。
現在、県と上関町には、電源立地地域対策交付金が、①上関原発が重要電源開発地点に指定されていることで、期間Cのステージで、原発の使用が開始された日の属する会計年度までの期間、毎会計年度の限度額8000万円が交付され続けることになっている。また、②令和5年度から使用済み燃料の貯蔵施設分が毎会計年度1億4千万円が知事が施設の設置同意をする年度まで交付され続ける事にもなっている。
そこで、①で、限度額8000万円を県が200万円、上関町が7800万円に分けて交付申請しているのは、何の根拠に基づくものか。伺います。
つぎに、上関原発は、海を埋め立てざるを得ない計画で、公有水面埋立の免許権者は県知事だから、次の埋立延長許可申請を認めなければ、おのずと原発の使用はあり得なくなるわけで、原発交付金の呪縛から逃れるためにも、庁内調整を図り、公有水面埋立の見直しの検討を始めるべきだが、見解を伺います。
さらに、②に関し、上関町町議会への決算報告書で、令和5年度、6年度の使用済み燃料の貯蔵施設分の交付金が交付されていることが明らかになっているが、これは、県と上関町に交付金を交付される性質のものだから、県は受け取る気はないと言えども、上関町への交付金を公開すべきである。伺います。
最後に、1974年の創設当時の電源三法交付金の使途は、知事が自治体と電力会社の意見を聴いて、国の同意を得て作成した公共用施設整備計画に基づく事業の経費に限られていたが、改正が続き、維持管理費やソフト事業にも拡大され、使途は、住民への基礎的サービスが多くを占めるようになっており、交付金の使途をなし崩しにして一般財源とさほど変わらなくしていることは、一般論として基礎的サービスに必要な経費は普通交付税処置されていることと矛盾しているのではないか。見解をお聞かせください。
産業労働部理事答弁・・・原発に係る電源立地地域対策交付金についての(1)上関原発に係る電源立地地域対策交付金の県と上関町への額の配分、(3)使用済燃料中間貯蔵施設に係る電源立地地域対策交付金の公開、(4)電源立地地域対策交付金の使途拡大に関する見解についてのお尋ねにお答えします。
まず、上関原発に係る電源立地地域対策交付金の県と上関町への額の配分についてですが、事業実績等を勘案し、国との協議により決定されています。
次に、使用済燃料中間貯蔵施設に係る電源立地地域対策交付金の公開についてです。
お示しの交付金は、国と上関町との間で直接、申請や交付が行われるものであり、県はその手続に関与をしていません。
また、現時点、県は当該交付金を活用して事業を行うことは考えておらず、上関町のみに交付されている交付金については、県が独自に明らかにすることは考えていません。
次に、電源立地地域対策交付金の使途拡大に対する見解についてです。
電源立地地域対策交付金は国の制度であり、お示しのような事柄について、県が独自に見解を述べることは考えていません。
土木建築部長答弁・・・原発関連の御質問のうち、(2)公有水面埋立免許の見直しの検討についてのお尋ねにお答えします。
県としては、今後、免許延長の申請がなされた場合には、その時点において、公有水面埋立法に従って厳正に審査し、適正に対処することとしており、見直しを検討することは考えていません。
| 再質問・・・上関町の令和5年度電源交付金を活用した事業概要の公表資料で、社会教育施設維持運営事業、地域医療等維持運営事業など全11事業に7800万円、使途は主に人件費、電気代、水道料、浄化槽管理委託料などです。更に加えて視察研修事業で東海原発使用済燃料貯蔵施設を含む視察や、総合計画策定基金造成事業、診療所施設設計基金造成事業の3事業に合計で69,957,500円が交付されています。令和6年度には社会教育施設維持運営費など12事業に1憶3800万円と視察研修事業に200万円の計1億4000万円の電源立地地域対策交付金が交付されています。
しかし、診療所施設建設基金造成事業に7800万円を上関町は予定をしていましたが、5年度で建設予定地の既存施設解体造成費に交付金を使ったものの、軟弱液状化地盤で建設不可で実績額0円となっています。 決算特別委員会の資料には、上関町への電源立地対策交付金は令和5年度分7800万円、令和6年度分は0円と報告しており、これに対する説明は、上関町への交付金は町に直接交付されるが、重要電源開発地点分、つまり原発建設のための交付金の限度額は8000万円で、県も200万円申請しているので、限度額を超えない確認をする必要があるので公表している、であった。 そこで、令和5年度から使用済核燃料の貯蔵施設分も交付されているので、両方の交付金を合わせて公表しないと、限度額超過に関する説明にもならないと思うが、再度お尋ねします。 それともう一点、一般的経費にも使われていることについて、交付税措置との関連についてお答えがありませんでしたけども、お聞かせください。 |
商工労働部理事答弁・・・原発に係る電源立地地域対策交付金についての再質問にお答えします。まず、上関町に交付される交付金についてですが、電源立地地域対策交付金の1会計年度の限度額は、上関原発に係るもの、使用済燃料中間貯蔵施設に係るもの、それぞれ別に設定されており、限度額を超過するか否かはそれぞれの限度額に照らして判断されるものです。
お示しの県決算特別委員会の資料における数値は、上関原発に係るものであり、県と上関町が活用していることから、県と町の配分額の合計が、上関原発に係る交付金の限度額8000万円の範囲内とする必要があります。
このため、県としても上関町に係る交付金について把握をし、提出したものであり、資料の内容に問題があるとは考えていません。
次に、電源立地地域対策交付金の使途拡大に関する見解についてです。
先ほども申し上げましたが、電源立地地域対策交付金は国の制度であり、お示しのような事柄について、県が独自に見解を述べることは考えていません。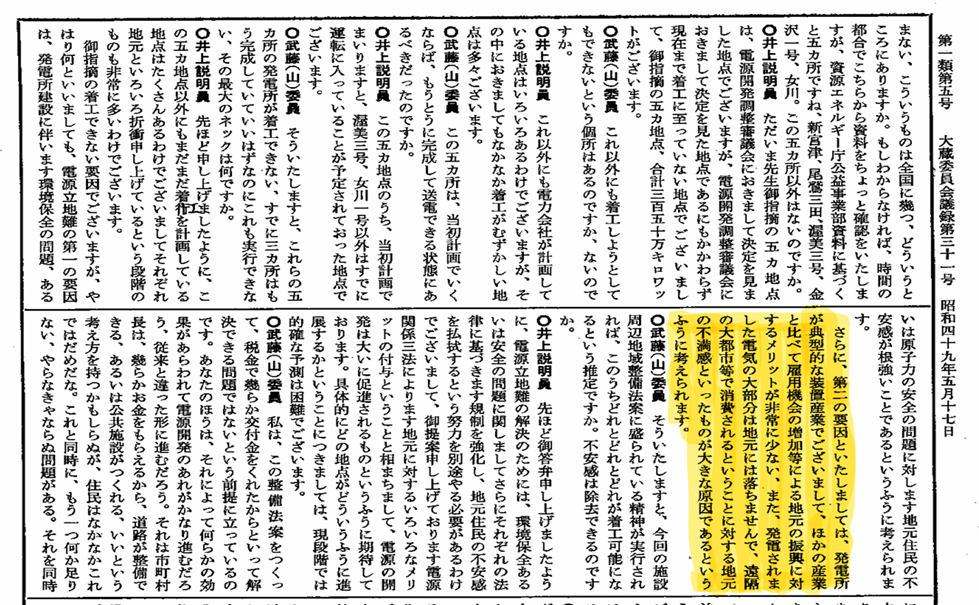
不登校児童生徒への支援について
25年11月県議会
5、不登校児童生徒への支援について
文科省の誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策、COCOLOプランについて、令和5年6月定例会及び11月定例化でも質問しましたが、今回は視点を変えて、不登校児童生徒への支援について伺います。
決算特別委員会資料によると2023年度県内国公私立学校の不登校児童生徒数は、小学校1284名、中学校2286名、高等学校387名、合計3957名、特に中学校では出現率68.0と増加の一途をたどっています。
さて、学校では、学校保健安全法に基づいて、毎年六月までに定期健康診断を行っています。検査は、身体測定、視力、聴力、内科、歯科、眼科、耳鼻咽喉科など多岐に及んでいます。近年急増している不登校児童生徒の中には、この健康診断を受けていない子供がおそらく三分の一から半分近くではないかとの話を聞きました。
そこで、教育長に学校で行われる健康診断の果たす役割についてどのように認識されているのかお聞きした上で、県教委として子供たちの健康状況を知る上でも、市町立学校を含め、健康診断の実施状況を把握すべきと考えますが、お考えをお伺いします。
次に、本県の県立高等学校における不登校児童生徒の健康診断の実施状況はどうなのか。また、健康診断を受けることができなかった生徒やその保護者に対してどのような対応を行っているのかお聞かせください。
健康診断を受けていない子供が後日、医療機関で健康診断を受ける場合、自費になります。健康診断は保険適用外ですから費用がかかり、診断を受けない選択をせざるを得ない場合もあると思います。今後、医師会などと連携するなど、健康診断を受けていない子供に対して何らかの対応が必要と考えますが、教育長のお考えをお聞かせください。
次に、学習意欲のある不登校児童生徒への支援について伺います。
文科省の調査によると、不登校児童生徒のうち、教育支援センターやフリースクールなどの支援機関を利用しているのは4割程度となっています。つまり、一定数の子供は引き籠もった状況であることが推察できます。このような外出が困難な子供に対する学びの選択肢は多いほうがよいと考えます。
例えば、障がい者就労支援の一つの方法として、神奈川県では、令和4年度から外出が困難な障がい者を県職員(会計年度任用職員)として任用して、分身ロボットOriHimeを活用した遠隔操作により、「ともに生きる社会かながわ憲章」のPR業務などの事業が行われ、従事された職員の方は、OriHimeを通じて、家にいながらお客様と同じ時を共有でき、多くの方の笑顔に出会うことができます。この活動が、誰かにとって就労の新しい選択肢になれたら嬉しいです。と述べられています。
また、鳥取県教育委員会では、希望する公立学校に分身ロボットOriHimeを貸し出す「病気療養児の遠隔教育支援事業」を展開しています。
学校に通学することができない児童生徒にとって、OriHimeを使って参加することで学習意欲の向上が図られることが実証されています。これは病気や障がいのある生徒に限ったことではないと私は思います。
文科省の調査では、学校に戻りやすい対応として、友達からの声がけが2番目に多くなっています。OriHimeはタブレットとは違い、ロボットの動作や音声によって自分の意思を表現したり、周囲と交流することができます。このような特性を生かし、不登校児童生徒への授業参加に活用してみてはと考えます。もちろん導入に当たっては、本人や保護者、学校や教員の意見を十分聞く必要があると思いますが、教育長のお考えをお聞かせください。
真摯な答弁を期待しています。
副教育長答弁・・・不登校児童生徒への支援についての、数点のお尋ねにお答えします。
まず、学校で行われる健康診断の果たす役割の認識と、実施状況の把握についてです。
学校における健康診断は、児童生徒の健康状態を把握するとともに、学校における健康課題を明らかにして健康教育に役立てる役割があると認識しています。
また、その実施状況については、実施主体である学校において把握しており、市町教委や学校から相談があった場合には、県教委としても、指導・助言等を行っているところです。
次に、県立高校における不登校生徒の健康診断の実施状況と、健康診断を受けることができなかった生徒や、その保護者に対しての対応についてです。
県立高校の不登校生徒の健康診断についても、学校において、実施状況を把握するとともに、不登校生徒や、その保護者に対して、家庭訪問等により、生徒の健康状態を確認した上で、学校医等と相談し、学校医の診療所等で健康診断の受診を勧める対応を行っています。
次に、健康診断を受けていない子供が後日、医療機関で健康診断を受ける場合の対応についてです。
学校では、学校医等と相談し、学校医の診療所等で健康診断を自己負担なく受けることができる対応も行っているところです。
次に、分身ロボットOriHimeを活用した不登校児童生徒の授業参加についてです。
学校では、病気療養中や不登校の児童生徒に対する遠隔授業を実施する場合には、教材のやり取りや、互いに顔を合わせたオンライン授業が可能な、1人1台端末を活用することが一般的ですが、県立学校では、児童生徒の状況により、学校から要望があった場合には、県教委がOriHimeの貸し出しも行っているところです。
県教委といたしましては、不登校児童生徒の健康診断を受ける機会の確保や学習支援など、引き続き、不登校対策に取り組んでまいります。
孤独・孤立対策について
25年11月県議会
4、孤独・孤立対策について
非正規労働者の増加、少子・高齢化や核家族化、未婚化、晩婚化など、単身世帯や単身高齢者の増加により、低賃金や低年金者層を中心に、孤独・孤立が生まれやすい社会となっています。孤独・孤立対策推進法に基づき、地域共生社会の実現に向け伺います。
今年4月、警察庁は2020年に一人暮らしの自宅で亡くなった人は76,020人と発表。また、内閣府は警察庁のこのデータをもとに死後8日以上経過して発見されたケースは生前に社会的に孤立していたことが強く確認されることから「孤立死」として位置づけて21,856人と発表しています。2024年県内において、自宅で死亡した独り暮らしの人数は1187人。そのうち65歳以上が948人で、孤独死は高齢者に限った問題ではないことも明らかとなっています。
2020年の国勢調査によると、本県の世帯数は59万7309世帯。そのうち単独世帯は21万8208世帯で、36.6%となっています。県内においても人間関係が希薄となり、引取り手がいない遺体が増えているのではと推測されます。
また、社会的孤立が自殺の引き金となっているとの調査結果があります。自殺者の減少は見通せず、2024年は本県で252人。県内では毎年200人以上、全国では2万人以上が自殺しています。
本県として、こうした孤独・孤立対策にどのように向き合って対策を講じられているのかお聞かせください。
健康福祉部長答弁・・・孤独・孤立対策についてのお尋ねにお答えします。地域におけるつながりが希薄化し、支え合い機能の低下が進行する中、社会的な孤独・孤立を防止するため、多様な機関と連携しながら、誰一人取り残さない包括的な支援体制の整備を進めているところです。
具体的には、民生委員や企業等と連携した訪問や電話など、様々な機会を捉えた見守り活動を行うとともに、地域住民が抱える複雑化・複合化する課題やニーズに対して、行政機関や福祉関係団体、NPО法人等、多様な支援機関が協働して解決に向けて取り組んでいます。
さらに、こども食堂等の、世代や属性を超えて住民同士が交流できる居場所づくりの促進のほか、ボランティア活動等の社会参加への支援など、総合的に取組を進めているところです。
県としましては、引き続き、人と人とのつながりを実感できる地域共生社会の実現に向けて、多様な機関と連携しながら、孤独・孤立対策に取り組んでまいります。
| 再質問・・・ひきこもり、ヤングケアラー、不登校など、若者から高齢者の全世代における孤独・孤立化が深刻化している中、法律に基づき「孤独・孤立対策地域協議会」の設置が法で努力義務化されている。答弁では特に触れられなかったが、県内における検討あるいは設置状況はどうなっているのか伺う。 |
健康福祉部長答弁・・・孤独・孤立対策についての再質問にお答えします。孤独・孤立対策地域協議会については、県内には設置されていませんが、県では、孤独・孤立対策も含めた地域住民の複合化・複雑化した支援ニーズに対応するため、多様な支援機関が協働した重層的な支援体制の整備を進めているところであり、現在、6市において、体制が構築されています。
集落営農法人への支援について
25年11月県議会
3、集落営農法人への支援について
昨年後半からのコメ不足による米価高騰騒ぎが起きているが、長年の米価低迷と10a当たり1万5千円あった米の直接支払い交付金が7500円になり2018年度には、これも廃止になるなど、稲作中心の本県農業を取り巻く状況は厳しさを増し、活路を求めて集落営農法人を推進し、地域のみんなが参加し農地を守る体制づくりを打ち出してきた。
県内の集落営農法人は、2010年度116法人であったものが2024年度で303法人に増加しているものの、2020年農林業センサスによる本県の農業従事者の平均年齢は72.3歳と全国平均よりも高く、2025年の確定値ではさらに高くなっている筈だから、現在ある集落営農法人を維持していくことも容易ではありません。今後も集落営農を推進することはいいのですが、高齢化が進み、組織があっても作業できる人がどんどん減っている状況が私の住んでいる地域でも見られます。これからは、新たな集落営農法人の設立とともに、既存法人をどうフォローアップしていくかが重要です。できた法人を放っておけば、潰れるようなことがあってはなりません。
周りからも、①集落営農を立ち上げたがオペレーターが高齢化し、世代交代が進まない。②本県は条件不利地域を多く抱えることから農地集積の面積規模が小さい。③収益性の低下。などの悩みを聞かされます。
これらへの対策として、2015年から「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に集落営農法人連合体の育成が位置づけられ、「担い手支援日本一対策」の創出、さらに、2022年度に新設した農業経営・就農支援センターを核に農業中核経営体の育成と経営基盤の強化などの対策を講じられています。
そこで、お尋ねです。集落営農法人の平均耕地面積の調査データは現在無いとのことだが2015年度末は平均で26.3haだったそうで、現在も変わりないのが本県農業の実態だろうと思われ、20~30ha規模の経営で、十分な所得が得られる専従オペレーターと、農地の出し手であり軽作業を分担する担い手でもある多数の構成員とが、しっかり役割分担しながら持続可能な山口県版経営モデルを確立しなければならないのではと思います。そのために地域の特性にあったきめ細かな指導・支援体制を、財政支援を含めて、県として構築すべきではと思いますが、どのようにお考えか伺います。
農林水産部長答弁・・・集落営農法人への支援についてのお尋ねにお答えします。中山間地域が県土の約7割を占め、全国より早いペースで農業従事者の高齢化が進む本県では、持続可能な農業の実現に向け、市町やJA等関係団体と連携し、地域農業の中核的担い手である集落営農法人の経営基盤強化と併せて、法人後継者の確保に向けたきめ細かな取組を進めています。
具体的には、まず、経営基盤強化の取組として、農地の維持が困難となった法人との経営統合により規模拡大を目指す法人に対して、アドバイザー派遣による経営安定ビジョンの作成を支援するとともに、その実現に必要な農業技術やスマート農機等の導入に対する支援を行っています。
次に、法人後継者確保の取組として、就農フェアや就業ガイダンス等を通じて、全国トップ水準の給付制度等をPRするとともに、法人代表者と直接面談できる場の設定により、社会人インターンシップへの参加に繋げるなど、法人への就業を促進しています。
| 再質問・・・11月23日付けの日本農業新聞に県内の集落営農法人303のうち3割が農大卒業生・移住者らを正社員雇用、またJA・県が法人の収益拡大支援との記事が喜ばしい限りです。しかし、303法人のうち3割ですから、あと200法人の経営・営農が、この先五年、十年、どうなるのかが心配なんです。農林水産業振興計画での、例えば、オペレーターなども行う農業中核経営体数が2026年目標値550経営体で大丈夫なのか、そもそも達成の見込みがあるのかお尋ねいたします。 |
農林水産部長答弁・・・集落営農法人の支援に係る再質問にお答えいたします。農業新聞に、県内の集落法人の303の3割が農大卒業生・移住者らを正社員雇用しているという記事が出ていたと。で、残りの200法人の集落営農法人の五年、十年の経営・営農はどうなるのか心配だと。県の振興計画で、農業中核経営体について2026年目標を550経営体としているが、それで大丈夫なのか、そもそも達成の見込みがあるのかという質問だったかと思います。
まず中核経営体の数、お示しの数ですが、令和6年度末で、お示しの、言われたですね、集落営農法人303経営体ございまして、それを含めて516経営体となっております。令和8年度末の目標、これがあの550ということですけれども、これには達しておりませんが、市町や関係団体と連携いたしまして、地域計画に基づきます協議を進め、引き続き農地の基盤整備等に合わせてですね、新たな法人の設立を推進するとともに、今後規模拡大を図ろうとする株式会社等の企業の参入、こちらの方もですね、促進をですね、しているところでございます。以上です。